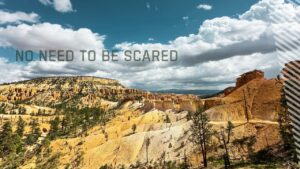こんにちは、さやかです。
最近の子育てのテーマは、
「宿題」。
ついにやってきたかこのテーマ、
という感じですが笑
日本人補習校の宿題が多すぎて、
親子で日々バトルです。
補習校の宿題は印刷や問題作成など
何かと親の負担も多いモノ。
時間をかけて準備をしても、
「また宿題?」
「なんでこんなことやらせるの?」
「仕方ないからやってやる」
と言った態度をとられると、
プツリ。
ガミガミ言わない方がいいのかと
自主性に任せようとしても、
それはそれで全くやる気配なし。
「やらなくて困るのは自分で、
自分のためにやるんだよ」
と言ったところで全く心に響かない。
「漢字」だけは学んでほしい
という親としての気持ちがあって、
宿題バトルが続いていました。
しばらくモヤモヤしていましたが、
「宿題」について
さまざまに試行錯誤する中で、
少しずつ方向性が見えてきました。
やり方はいくらでもある
まずは、
子どもが必要性を感じていないのに
自主的にやろうとする訳がないよね、
ということ。
「モノで釣ってやらせる」
というのは違和感を感じますが、
でも何か行動をする時に
必要性や目的があることって、
まずは必要なのだと思います。
知りたい、理解したい、
できるようになりたい、
といったような。
今の時代は色々な「やり方」も出ている訳で、
・漢字練習帳に340字以上/週
・原稿用紙に400字以上視写/週
・漢字ドリル10ページ以上/週
だけが漢字を身につける方法ではないよね、
ということに気づきました。
無意識のうちにいつの間にか、
学校から指定されるやり方に
固執していましたが、
決してそれが全てではない。
子どもの探究心をくすぐるような、
子供自身が必要性を感じるような方法を
自由に模索していこうと思いました。
親が信じていないことを子どもは察する
「宿題やりなさい」
「答えが見やすいように書きなさい」
「姿勢正しく座りなさい」
などなど。
こうした方がいい、
あぁした方がいいという、
親の小言。
子どもに必要なアドバイスをすることは、
もちろん必要なことだと思います。
人間の意識の中で、
タマス(怠惰、やる気のない、無気力)
という状態が一番強いと言われますが、
人は自分を甘やかしたら
どこまでも怠惰になる。
だから、
ある程度自分を律するように
親が導くことは必要です。
ただそのアドバイスが
「小言」になってしまって、
子ども達に響かないのはなぜなのか?
ここがポイント。
けむたがられたり、
うざがられるのはなぜなのか?
それを考えていくと、
アドバイスをする親の心のあり方に
要因があると気づきます。
「こうした方がいいよ」
「それはしない方がいいよ」
「これをやった方がいいよ」
その言葉を発する親側の心のベースが
不安や心配といった「疑い/恐れ」だと、
その言葉は相手に響かない。
親自身が子どものことや
子供の人生を疑っていると、
その言葉は子どもに届かない
ということ。
みんなやっているから
やらせとかないと不安、
ちゃんとできるようにならないと
ダメな大人になりそうで心配、
この子の人生失敗したら大変、
などなど。
そんな「恐れ」をベースに導こうとしても、
子どもには何も響かないのです。
ではどうすればいいのかというと、
その子自身や、その子の人生、
もっと言えばこの世界の完全性を
どこまでも信じること。
「今を感じていく時に
それがあなたには必要不可欠なピースだと
心から感じるからこそ、
取り組んで経験してみてほしい」と、
信じるという愛を心のベースに
伝えていくことです。
親の心のベースがどこにあるのか、
・未来への恐れから言っているのか
・自分を信じて言っているのか
子どもは的確に見抜きます。
そして、
子どもや子どもの人生を信じ切るためには
親自身が自分自身を信じ切る必要がある。
親自身が自分自身を信じ切るためには、
親自身が自己を深く理解し、
ジャッジを手放していく姿勢が
とても大切です。
子どもに伝える言葉が
なかなか響かない。
そんな時は、
自分の心のベースを見つめてみると、
いいかもしれません。
おわりに
たかが宿題、されど宿題、
子育ては本当に学ぶことばかりです。
イライラする事象に惑わされずに、
その事象が指し示す本質を見ていく。
その姿勢がどんな時も
人生においてとても大切ですね。
今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
では、また!